平塚市博物館公式ページ
「相模川の生い立ちを探る会」
活動の記録
第215回 2010年10月16日 初島
■ テーマ:初島の地形・溶岩と海洋観測
■ コース:熱海港~初島港~初島海洋資料館~北西海岸~西海岸~灯台~東海岸
今回の目的は、初島の地形・溶岩を観察して、初島の地質を理解することと、初島の海洋資料館やケーブル流入口を見ることで、海洋観側の現場の様子を知ることでした。
熱海港を出航して船内で三ツ石・真鶴岬~幕山~大室山に至る稜線を眺めながら、箱根火山や伊豆東部の火山の地質や地形(溶岩ドーム・寄生火山・海食崖など)の説明を森先生から受けました。初島に近づくと、初島は平坦な台地状をした島でした。これは海面下で浸食された波食台が、地震の度に隆起を繰り返して形成されたものとのことでした。南西の一角に活断層が知られていること(柏木・櫻井, 1987)、平らではあるがやや西側が高く北西に傾いているとの説明もありました。
初島港に着いて、まずJAMSTECの初島海洋資料館に寄りました。詳細な海底地形模型を見ながら、相模湾地域のプレート・火山フロント・海丘などの配置とテクトニクスについて説明をしていただき、よく理解できました。
資料館を出てから、反時計回りに海岸沿いを進みました。初島の北西側にある竜神宮の先の海岸の露頭で、流理の発達した無斑晶質の縞状安山岩質玄武岩を確認しました。色調からすると安山岩のように見えます。縞状の流理は数 cm幅で石基の粒子が異なっているからでした。転石には、輝石安山岩・含輝石カンラン石玄武岩が多数ありました。
その後西側海岸に廻り、遊歩道が切れたところから海に出ると、深海底総合観測ステーションへ伸びるケーブル(径20
cm位の鉄製の管)が海中へ流入していました。深海底総合観測ステーションは、1993
年9 月に海洋研究開発機構 (JAMSTEC) が、初島南東沖6 km、水深1174 mのシロウリガイ群集域に世界で初めて設置し、長期連続観測を開始しました。その後、2000
年に新しい観測ステーションに更新し、観測を続けています。観測ステ-ションには、テレビカメラ、地震計、水圧計、流向流速計など多くの観測機器が装備され、観測データは、全長約9
kmの光電気複合ケーブルを介して初島に送られます。この観測の目的は、シロウリガイの活動、コロニー下の地殻熱流量、伊豆半島東方沖の群発地震、手石海丘などの火山活動などを長期にわたって、多面的にかつリアルタイムで観測し、それらの因果関係を明らかにすることだそうです(以上JAMSTEC
HP)。またこの海岸は斜長石に富むカンラン石玄武岩の巨礫だらけでした。カンラン石玄武岩には、カンラン石ハンレイ岩(最大28
×34 mm)の捕獲岩を含むものがありました。また、斜長石に富むカンラン石玄武岩中にカンラン石玄武岩を捕獲したように見えるものがありましたが、これは同質のカンラン石玄武岩とのことでした。その少し南にある海岸には斜長石の大結晶を含んだ斑状のカンラン石玄武岩の露頭がありました。斜長石の大きな捕獲結晶(マグマが上昇する際に,途中の岩石を壊して取り込まれた結晶、そのマグマに由来しない結晶)が入っており、新しい発見で大いに士気が上がりました。
海岸から離れ、段丘崖をあがって周遊道路が走る平坦面は標高34 mほどで、さらに上がると標高50 mほどの初島灯台の平坦面となっていました。この2つの平坦面は、前者が三崎面(約7 万年前)、後者が小原台面(約9 万年前)(杉原 1980)ということで、9 万年間で50 m隆起したことを示しているとのことでした。灯台に登ると、小原台面が望め、かすんでいましたが、わずかに富士山も認められ、360 度のパノラマを楽しんで記念写真を撮りました。
東海岸の海泉浴「島の湯」前では、流理が垂直に立ったカンラン石を含まない安山岩質玄武岩を観察し、火道に近い可能性もあるのではないかとの説明がありました。東海岸では西海岸より巨礫が多く、最初の地点で見た縞状溶岩も見あたりませんでした。江戸城修築に用いた石切場跡がある辺りも、カンラン石のほとんど入っていない安山岩質玄武岩でした。
結論としては、初島の溶岩は灰色を呈した無斑晶質の縞状安山岩質玄武岩溶岩と、カンラン石玄武岩の2種に大きく分かれるとのことです。前者からは60 ~70 万年前、後者からは30 万年前以降のK-Ar年代が得られている(及川・石塚2011)ということです。空には半月、夕日が伊豆の連山に沈んでいく中、カモメとともに熱海港に戻りました。(M. I. &S. M. )
文献
柏木 修一・櫻井一賀 (1987) 初島南部の活断層に関する資料. 活断層研究, 4, 37-41.
杉原重夫 (1980) 関東地方のテフロクロノロジー研究の現状と課題. 駿台史学, 50, 10, 286-295.
及川輝樹・石塚 治 (2011) 熱海地域の地質. 地域地質研究報告(5 万分の1 地質図幅), 産業技術総合研究所地質調査総合センター.
 |
 |
| ▲初島を洋上から見ると、海成段丘地形ということが良くわかる |
▲港の近くにある初島海洋資料館 |
 |
 |
| ▲無斑晶質の縞状安山岩質玄武岩の露頭を観察する(北西海岸) |
▲流理の発達した無斑晶質の縞状安山岩質玄武岩 |
 |
 |
| ▲深海底総合観測ステーションへ伸びる海底ケーブル(西海岸) |
▲カンラン石ハンレイ岩の捕獲結晶を含むカンラン石玄武岩(北西海岸) |
 |
 |
| ▲カンラン石玄武岩の捕獲岩を含む玄武岩溶岩(西海岸) |
▲斜長石の捕獲結晶の入るカンラン石玄武岩(北西海岸) |
 |
 |
| ▲燈台が位置する小原台面。9万年間で50 m隆起したことがわかる |
▲灯台に登り、灯台のある小原台面を望む |
 |
 |
| ▲東海岸には西海岸より巨礫が目立つ |
▲この奥に江戸城修築に用いた石切場跡がある(東海岸)。 |
→活動の記録へ戻る
→大地の声へ戻る
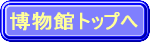
電話:0463‐33‐5111 Fax.0463-31-3949


