
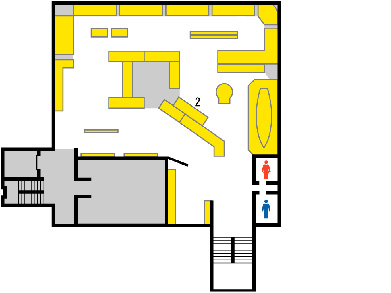
●漂着物を拾う会
博物館では、1990年から毎月「漂着物を拾う会」を開いてきました。虹ヶ浜の海岸を歩いて波に打ち上げられた物を拾い、それが何なのか、どこから来たのかなどをみんなで考える会す。海辺でのそうした活動は、ビーチコーミングの名で呼ばれ、近年全国で盛んになってきています。
その会では、今までの活動でいろいろな物を見つけてきました。その資料を二つのコーナーで紹介しました。

漂着物を拾う会
●虹ヶ浜の貝
虹ヶ浜海岸は、長い砂浜の一角に位置しています。そうした環境のために、鎌倉や逗子のように近くに磯のある海岸に比べると貝の種類は多くはありません。それでも、会を15年間以上続けてきたので、見つけた貝も150種類を越えています。その中で代表的な種類はダンベイキサゴです。この貝は、五領ヶ台貝塚の大部分を占める種類ですから、その当時から平塚の海に多かったようで、この貝が見つかれば、平塚海岸の環境も昔とそれほど変わっていないと考えることができます。そうした意味で、平塚の海の健康を示す大事な種類です。
拾った二枚貝を調べると、頭の部分にきれいな丸い穴が開いているものがよく見つかります。これはツメタガイという巻き貝に襲われて食べられた証拠です。虹ヶ浜の沖には、多くのツメタガイが生息しているようで、穴を開けられた貝殻が多く拾えます。波打際で拾う貝からも、海の中の生活が想像できるのです。


ダンベイキサゴ ツメタガイ(円内)と穴を開けられたコタマガイ
●虹ヶ浜とウミガメ
かっての湘南海岸はアカウミガメがよく産卵に訪れていました。現在でも、大磯・片瀬などで年に1回は産卵が確認され、虹ヶ浜でも子ガメが観察されたことがあります。 また、時には死体が漂着することもあり、相模湾にアカウミガメが定期的に訪れていることは確かです。展示した剥製と骨格標本はどちらも平塚海岸に流れ着いたものです。 アカウミガメが安心して卵を産むには、静かで車や人家の灯りが届かない暗い浜が必要です。そうした条件の浜を取り戻したいものです。
 漂着したアカウミガメ
漂着したアカウミガメ●遠くの海から
浜に打ち上げられた物の中には、海流に乗って遠くから運ばれてきたものが見つかることがあります。その証拠となるのがエボシガイがついているということです。エボシガイは、甲殻類に属し、プランクトンとして海に浮かんで暮らしている幼生が、海面に浮かぶ物にとりつき、殻のある体を作って成長する生活を送っています。大きなエボシガイがついていれば、少なくとも数ヶ月は流れてきた物でしょう。

エボシガイ
●熱帯からの果実
黒潮に乗って流れてきたことが確実なものに熱帯にしか生えていない樹木の果実があります。ココヤシはその代表ですが、虹ヶ浜では今までに、ゴバンノアシ・サキシマスオウノキ・モモタナマなどの実を見つけることができました。これらは、日本国内では沖縄に行かないと見られない種類です。ささくれだった表面や、エボシガイがついていることが、長い海流の旅を示しています。

ゴバンノアシ
●黒潮に乗る生活
動物の中には、海面に浮かび、海流に乗って移動しながら生活している種類が見られます。カツオノエボシ・カツオノカンムリ・ギンカクラゲなどの青いクラゲ類はその代表です。そして、それらのクラゲ類を餌にしているルリガイ・アサガオガイなどの青い殻を持った巻き貝も海流に乗って暮らしています。これらの動物は時にまとまって流れ着くことがあります。

カツオノエボシ