| まぎれこみ型とにげだし型の割合 | どこから逃げ出した種類が多いか |
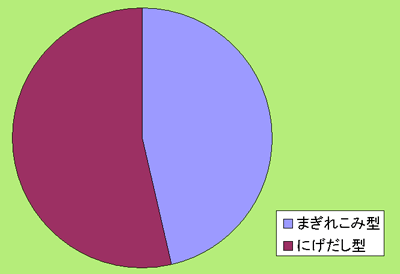 |
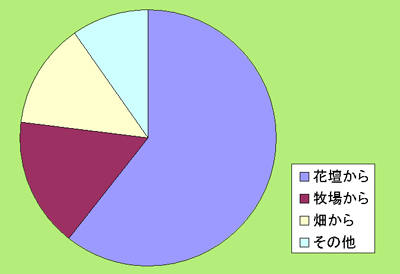 |
帰化植物はどうやって来たか? (2006.7)
探偵「まず、帰化植物がどうやって日本に入ってきたかだけど、君たちに何か考えがあるかな。」
物子「外国から輸入された大豆とか麦に雑草のたねがまぎれこんでいたという話を聞いたことがあるわ。」
博「花壇で作っていた種類が逃げ出して野生化することもあるんじゃないかな。」
探偵「そうだね。帰化植物が野生化するには、大きく見て二通りの道がある。物子ちゃんの言うような『まぎれこみ型』と、博君の言うような『にげだし型』の二つだ。」
物子「『まぎれこみ型』の場合、大豆や麦のほかに何にまぎれこむことがあるのかな。」
探偵「牛や馬の餌として輸入されている穀類(こくるい)にまぎれてくるものも多いらしい。毛織物(けおりもの)を作るのに輸入される羊の毛についた草の実が入ってくることもあるよ。いろいろなものを運ぶための布袋(ぬのぶくろ)に実がついてくることだって考えられる。」
博「ということは、帰化植物は外国から荷物が運ばれてくる港には種類が多いということになるのかな。」
探偵「その通りだ。港の空き地とか、荷物置き場のまわりには変わった種類が見つかることが多い。ただね、そういう植物がみんな帰化植物というわけじゃないんだよ。」
博「どうしてなの。」
探偵「日本にたねが入ってきて芽生えたとしても、途中でかれてしまう場合もあるし、2,3年そのあたりに生えているだけで、そのうちに消えてしまうものも多い。帰化というからには、そこから広がっていかないとね。」
物子「帰化植物の予備軍(よびぐん)もいるということね。」
| まぎれこみ型とにげだし型の割合 | どこから逃げ出した種類が多いか |
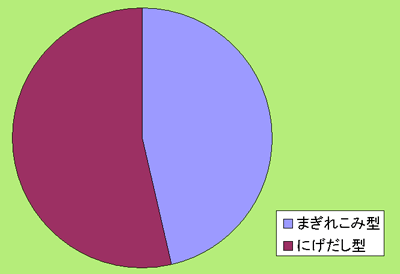 |
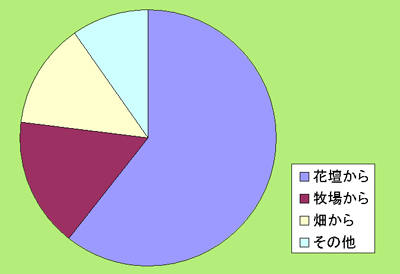 |
まぎれこみ型・花壇からのにげだし型・牧場からのにげだし型・畑からのにげだし型
探偵「『にげだし型』では、どんな所から逃げ出すものがあると思う?」
博「まず花壇だよね。それから畑かな。」
物子「もしかして牧場というのもありかな。牧草が野生化したという話を聞いたことがある。」
探偵「だいたいでそろったかな。割合でみてみると、花壇からにげだしたものが半分以上だね。」
物子「その他というのはどんな種類なの。」
探偵「ベニバナは染料(せんりょう)をとるために栽培されたものが野生化した。エビスグサのように薬草もあるね。コリヤナギという木は、柳行李(やなぎごうり)という着物なんかをしまっておくための箱を編むために栽培されていたものがにげだした。」
博「いろいろな役に立てようと輸入した植物が、いつのまにかにげだしたということなんだね。」
→ 帰化植物のトップへ
→ 自然探偵のトップへ
→ 平塚市博物館トップへ